【789人に調査】~宅食弁当・食材宅配サービスの利用についての意識に関するアンケート~
配信日時: 2023-05-30 10:00:00
食の窓口が「宅食弁当・食材宅配サービスの利用ついての意識に関するアンケート調査」を実施
株式会社アクロスソリューションズと一般社団法人 日本唐揚協会が共同運営している食の窓口(URL:https://karaage.ne.jp/contents/ )は、20歳~60歳以上の男女789人を対象に「宅食弁当の利用についての意識に関するアンケート調査」を実施しました。
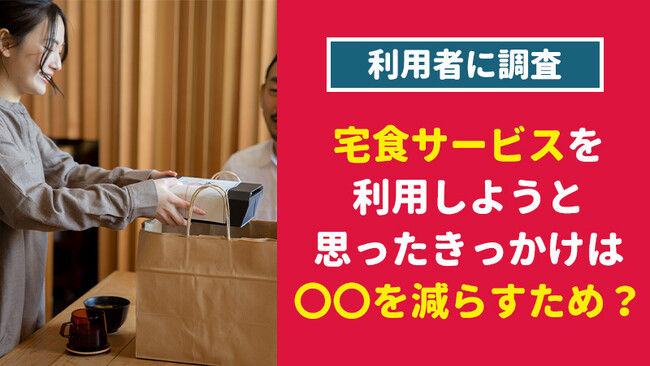
新鮮かつ栄養バランスの取れた弁当を運んでくれる便利な宅食弁当や食材宅配サービス。家で使うものだからこそ、周りの人がどんな風にどれくらい使っているのかは見えづらいものです。
みんなはどんな宅食弁当や食材宅配サービスを利用しているの?
宅食弁当や食材宅配サービスを使うのはどんなとき?
[画像1: https://prtimes.jp/i/23552/67/resize/d23552-67-2abc6745f564ec13890e-4.jpg ]
そこで、株式会社アクロスソリューションズと一般社団法人 日本唐揚協会が共同運営している食の窓口(URL:https://karaage.ne.jp/contents/ )は、20歳~60歳以上の男女789人を対象に「宅食弁当や食材宅配サービスの利用についての意識に関するアンケート調査」を実施しました。
食に特化しているメディアとして、食生活の世の中の人々の実態をきちんと把握し、食生活のあり方に悩むインターネットユーザーへのヒントとなれることを目的としています。
【調査概要】
1-1. 調査期間
2023年5月12日~16日
1-2. 調査機関
調査実施会社:
株式会社アクロスソリューションズ
デジタルマーケティング事業本部
1-3. 調査対象
20代~60代以上の男女
1-4. 有効回答数
n=789
1-5. 調査方法(集計方法、算出方法)
インターネットによる任意回答
■質問内容
Q1 どの宅食・食材宅配サービスを利用したことがありますか?
Q2 宅食・食材宅配サービスを利用しようと思ったきっかけは何ですか?
Q3 今後、宅食・食材宅配サービスを利用するときに何を重視しますか?
Q4 1食あたりどれくらいの価格であれば宅食・食材宅配サービスを利用したいと思いますか?
■調査結果サマリー
Q1 「生協」を利用したことがあると答えた人が34.7%で最も多かった。60代では「ワタミの宅食」、20代では「デリバリーサービス(UberEats,出前館,飲食店の出前利用など)」が支持を集めた。
Q2 最も多かった「料理の手間を減らしたかった」の46.5%をはじめとして、時短や自炊を避けるためのツールとして宅食サービスが利用されている傾向が強かった。
Q3 「価格」を重視すると答えた人が最も多く、全体の60.2%だった。
Q4 最も多かった回答は年代や性別を問わず一定で30.5%が回答した「500円以下」だった。
Q1 どの宅食・食材宅配サービスを利用したことがありますか?
[画像2: https://prtimes.jp/i/23552/67/resize/d23552-67-55ad0bfa863216be1a5e-0.jpg ]
最も多かった回答は「生協」で全体の34.7%でした。。
性別・未既婚でも同じ傾向だったが、年代別の60代では「ワタミの宅食」が32.4%、20代では「デリバリーサービス(UberEats,出前館,飲食店の出前利用など)」が28.2%となり最も多い結果となりました。
【回答】
ワタミの宅食 29.4%
Oisix 24.1%
生協 34.7%
ナッシュ 16.3%
三ツ星ファーム 8.9%
デリバリーサービス(UberEats,出前館,飲食店の出前利用など) 26.5%
その他 22.7%
Q2 宅食・食材宅配サービスを利用しようと思ったきっかけは何ですか?
[画像3: https://prtimes.jp/i/23552/67/resize/d23552-67-ce9d47b9da77a27107bd-0.jpg ]
最も多かった回答は「料理の手間を減らしたかった」で46.5%でした。
また2番目、3番目に多かったのも「買い物に行く手間を減らしたかった」(40.8%)、「メニュー・献立を考えるのが面倒だった」(32.4%)となり、宅食弁当や食材宅配サービスが健康や経済的な理由ではなく手間を掛けずに食事をするためのツールとして使われていることが分かりました。
また健康面の利用理由「栄養バランスの取れた食事をしたいと思った」「塩分や糖質などを制限する必要があった」を選んだのは、未既婚だと未婚者、子供の有無だと子供がいない人のほうが多いことが分かりました。
【回答】
料理の手間を減らしたかった 46.5%
買い物に行く手間を減らしたかった 40.8%
メニュー・献立を考えるのが面倒だった 32.4%
栄養バランスの取れた食事をしたいと思った 26.7%
塩分や糖質などを制限する必要があった 16.1%
食費を節約したかった 13.2%
ダイエットや筋トレをしたかった 7.2%
その他 5.6%
Q3 宅食・食材宅配サービスを利用するときに何を重視しますか?
[画像4: https://prtimes.jp/i/23552/67/resize/d23552-67-e36204216c5cab00a5d5-0.jpg ]
宅食・食材宅配サービス利用の際に、今後重視したいと思っている項目で最も多かったのは「価格」で60.2%でした。
年代別の30代では「価格」を選んだ人が47.1%と決して少なくはなかったものの、「味」を選んだ人の数が上回り、51.2%という結果でした。
【回答】
価格 60.2%
味 55.1%
栄養バランス 41.4%
メニュー数 34.1%
ボリューム感 29.5%
品質管理や衛生面での安心感 24.7%
配達や受け取りの利便性 25.9%
お試しや都度購入などの購入システム 16.3%
冷凍・冷蔵・常温などのお届け状態 18%
会社やブランドの知名度 10%
その他 0.8%
Q4 1食あたりどれくらいの価格であれば宅食・食材宅配サービスを利用したいと思いますか?
[画像5: https://prtimes.jp/i/23552/67/resize/d23552-67-ee9b14506c4378096829-0.jpg ]
最も多かった回答は「500円以下」で30.5%でした。
この傾向は性別や年代、未既婚を問わず一定でした。
一食ワンコインという基準は理想的ではありますが、宅食弁当サービスは1食あたり600円程度のものが多く、現状だと少し高いと感じている人が多いのかもしれません。
【回答】
300円以下 9.4%
400円以下 13.2%
500円以下 30.5%
600円以下 15.7%
700円以下 12.5%
800円以下 8.4%
900円以下 2%
1000円以下 6%
1000円以上 2.3%
■食の窓口とは
食の窓口は、”食べる”という点に特化したコンテンツサイトです。
さらに”家で食べる”に特化してコンテンツを紹介しています。
株式会社アクロスソリューションズ(URL:https://www.b-rock.jp/ )と
一般社団法人 日本唐揚協会(URL:https://karaage.ne.jp/ )が共同運営しています。
現代人のライフスタイルやそれぞれの悩みに合わせて
食にまつわる疑問を解決できる窓口のようなメディアを目指しています。
今後、現在の食生活の実態を年代、性別ごとに調査、発信いたします。
---------------------------------------
※こちらの調査の結果は後日、食の窓口(URL:https://karaage.ne.jp/contents/ )上で掲載予定です。
本アンケート結果を利用される場合は、弊社運営サイト・調査結果掲載予定ページへの引用リンクをお願いいたします。
■掲載予定記事
https://karaage.ne.jp/contents/?p=405
https://karaage.ne.jp/contents/?p=468
無断での転載は固くお断りいたします。
---------------------------------------
【食の窓口運営会社概要】
株式会社アクロスソリューションズ
デジタルマーケティング事業本部
住所:東京都千代田区神田富山町21FKビル3F
代表取締役:野村 充史
URL:https://b-rock.jp/
※運営メディア
食の窓口( https://karaage.ne.jp/contents/ )
買取比較ちゃんねる( https://www.hamaya-corp.co.jp/media/ )
アニメのお時間です!(https://aucfan.com/vod/)
一般社団法人 日本唐揚協会
事務局:東京都渋谷区道玄坂2-11-6
TOP HILLS GARDEN 道玄坂1201
会長:やすひさ てっぺい
URL:https://karaage.ne.jp/
【アンケート調査実施会社】
株式会社アクロスソリューションズ
デジタルマーケティング事業本部
https://b-rock.jp/
PR TIMESプレスリリース詳細へ
スポンサードリンク
「アクロスソリューションズ デジタルマーケティング事業本部」のプレスリリース
スポンサードリンク
最新のプレスリリース
- EDに関する理解度調査を男性200名を対象に実施 約3割がEDの定義を勘違い05/30 12:00
- 「白磁のアーティスト」の日常を彩る美意識『白の中のカラフル 黒田泰蔵の暮らし』展 BAG-Brillia Art Gallery-にて6月10日(土)より開催05/30 11:45
- ラック、組織のセキュリティ対策状況を可視化する「情報セキュリティプランニング」を幅広い組織が利用しやすいサービスにリニューアル05/30 11:30
- 全国3,000人による50,000点以上の手づくり作品が集結!「ヨコハマハンドメイドマルシェ2023」7/1(土)2(日)に開催!05/30 11:30
- PRIMO RING PRIJECTとして富士山自然保護活動を実施しました05/30 11:15
- 最新のプレスリリースをもっと見る
