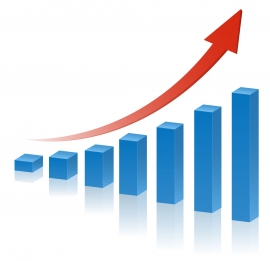関連記事
株式投資は博打などではない(終)
経営者を買うという株式市場の経験則がピタリと当て嵌まる企業人として忘れられないのが、クレディセゾンの社長を1983年から1994年まで務めた故竹内敏雄である。
【前回は】株式投資は博打などではない (5)
1985年のいわゆるプラザ合意が「失われた20年」ともされる日本経済の長期低迷の契機となった。「合意」の矛先は日本に向けられた。「ドル安・円高」の為替政策が世界の有力為替市場で執行されたのである。日本は翌86年、早々に円高不況に見舞われた。対峙策として政策金利(公定歩合)の切り下げ(当時としては史上最低水準の2・5%まで引き下げられた)が執られた。が、金融の緩和が日増しに進み、いわゆるバブル経済の華?が咲き乱れていったのである。
バブル経済の実態を顕著に示したのがノンバンクだった。預金機能を持たない貸付金融機関である。90年度末でノンバンクによる総貸付残高は約70兆円に達していた。70兆円という数字は当時の都銀の貸付残高の約4分の1、地銀全体の約2分の1水準であり長銀・信託銀行・第二地銀・信金信組の融資残高を上回っていた。ノンバンクの貸付の主体は不動産担保投資だった。
そんなバブル経済が崩壊の道を歩むことになったのは、「総量規制(銀行による貸し付け抑制)」であり公定歩合の急速な引き上げ。89年半ばから90年半ばの僅か1年間に5次にわたる引き上げで公定歩合は6%にまで上昇。総量規制という名目のもと銀行からの執拗な資金回収でノンバンクは昇っていた階段を外された。政策金利の急上昇で返済もままならなくなった。ノンバンクの業績は急転直下、天国から地獄に陥らざるをえなくなった。
そうした中で唯一例外だったノンバンクが竹内率いるクレディセゾンだった。バブル崩壊後も順調な収益展開をみせた。何故か。竹内の頑なまでの自らに課していた「経営哲学」の厳守に求められる。竹内の経営哲学の一つは「実験と学習」。
80年代も終盤にさしかかろうという頃、東京・池袋のサンシャインビルにあるクレディセゾンの社長室では連日のごとくこんな光景が見受けられた。
「社長、これでもダメか」と担当役員を先頭に融資部門のスタッフが、不動産担保融資の決裁を竹内に求めた。「投資先の成長性」「担保不動産の確実性」「抵当権の上位設定」をとうとうと説明しかつ、主要銀行からの融資資金付のどこに問題があるのかと迫ってくるのだった。だが竹内の答えはいつも「だめだ。僕がこの会社の社長でいる限り不動産担保融資はご法度」と決まっていた。
当時私に竹内は「僕は新しい事業が目の前に出てきた時、まず実験と学習をすることにしている」と打ち明け、具体的にこう語った。
「セゾンカードでの個人融資額は1件当たり3万円から3万5000円。需要が高まっていた法人融資は数百億円、千億円単位。僕も企業を預かる社長、利益は追いたい。そこで実験として約300億円の融資をやった。煮え湯を呑んだ。たとえば担保に差し出された不動産には借地権だとかなんだとか権利関係が怪奇といえるほど複雑。そして権利に絡んでくる人間が海千山千の一筋縄ではいかない面々揃い。担保の処分で実損は免れましたがほうほうの態で逃げ出した」
竹内はこうも言った。
「不動産担保融資は銀行のビジネスだと痛感した。銀行と勝負して勝てるはずがない。銀行は口座動向から貸付先の資金状況が常時チェックできる。万が一“危ない”と思えばサッと資金を引き上げることも可能。我々にはそれができない。それに担保不動産の付帯条項をじっくり読むと、そう簡単に右から左に処分できないような手枷足枷がいっぱい。だから法人融資の歴史と審査体制が整備されている銀行ですら時として不動産担保融資で躓く。“実験”からそれを実感したからこそ金輪際不動産担保融資には手を出さないと決めた」。
そして竹内が新規事業を判断する際に行う「学習」とは、こういうことだ。実験をしている最中に「日本の大手都銀が経営困難に陥った米国の大手ノンバンク××を買収する」という報道に接した。竹内は「僕は明日から2週間の予定で米国の××社に行き、伝手もえたので××のトップに10日ほど張り付いて経営難の理由を確かめくる」とし渡米した。社長室のスタッフに「帰ってくるまでに過去の世界の大手ノンバンクの破綻の理由を調べておくように」と言い残してである。帰国後の竹内はこう話してくれた。
「××社の困窮のトリガーは案の定、不動産担保融資。そして渡米前に頼んでおいたリサーチの報告書を見てあらためて確信した。欧米の代表的なノンバンクの破綻の原因は大方が不動産担保融資絡み。誰がなんと言おうと結果的に収益面で同業他社の後塵を拝すことになろうとも、首になるまで不動産担保融資はしない。代わりに法人金融は銀行や同業者も手薄の分野、リース業に注力しようと決めた」
新たな事業が目の前に垂れ下ってきた時、「実験と学習」の徹底で対応を決める。一度「ノー」と決めたら「首になるまで譲らない」という竹内式経営哲学が、クレディセゾンをしてバブル酒に酔いしれない稀有のノンバンクにした。
「金融業には金融業のセオリーがある。学者が机上で試算しはじきだした理論の類ではなく、金融業の歴史の中から産み落とされた定石。他社も頭では十二分に理解していただろうが実行しなかった。ギアリング比率に黄信号が点滅しているにもかかわらずだ」
ギアリング比率とは「有利子負債など他人資本÷自己資本」。ギアリング比率が12倍を超えてくると危険な状態とされる。クレディセゾン以外の各社には黄信号が点滅していた。
竹内が「買いたい経営者」であることは、詳細は省くがバブル崩壊後の株価動向が証明している。
ちなみにクレディセゾンの時価は1800円台前半。対してIFIS目標平均株価は「割安」の但し書き付きの2230円。上値余地を示している。
改めて記す。株式投資は博打などではない。(敬称、略)(記事:千葉明・記事一覧を見る)
スポンサードリンク
関連キーワード